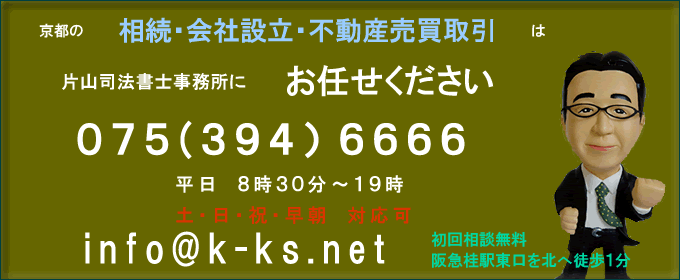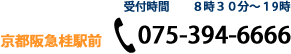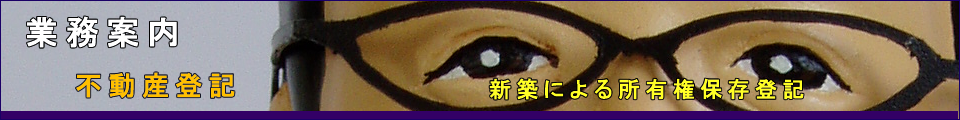新築による所有権保存登記
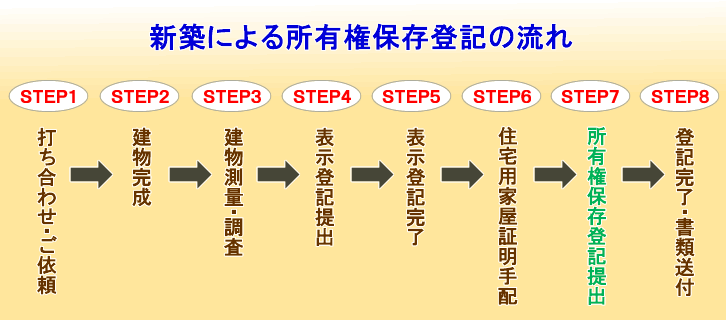
新築による所有権保存登記とは
建物を新築した場合の登記として、建物表示登記と所有権保存登記があります。
前者は表示の登記(建物表題登記)といわれ土地家屋調査士の業務で、後者は権利の登記といわれ、司法書士の業務となります。
通常、住宅ローンを組むことが多いため、金融機関の住宅ローン抵当権設定登記の前提として、これら2つの登記が必ず必要となります。
当事務所にご依頼いただいた場合、土地家屋調査士と連携して行いますので、住宅ローン抵当権設定登記までワンストップで行えます。
新築による所有権保存登記に必要な書類
- 1.住民票
- 2.住宅用家屋証明
- 3.委任状
※住宅用家屋証明は、取得できる場合、通常、土地家屋調査士が手配します。
※委任状は、当事務所にて作成致します。
新築による所有権保存登記の登記費用の目安
新築による所有権保存登記には、登録免許税や登記事項証明書等の実費と、司法書士報酬(消費税別途)がかかります。
登録免許税額は、「新築建物課税価格×税率」(下記事例の場合、1千万×0.15%=1万5千円)の要領で計算します。ただし、建物の種類等により下記のように税率が異なります。
住宅用家屋証明を取得できる場合の軽減税率
- 1.一般の建物の場合(租税特別措置法第72条の2) 新築建物課税価格×0.15%
- 2.特定認定長期優良住宅の場合(租税特別措置法第74条) 新築建物課税価格×0.1%
- 3.認定低炭素住宅の場合(租税特別措置法第74条の2) 新築建物課税価格×0.1%
住宅用家屋証明を取得できない場合の税率
- 新築建物課税価格×0.4%
新築による所有権保存登記の登記費用目安
| 参考事例:内訳 | 司法書士報酬 | 登録免許税等実費 |
| 所有権保存登記 | 19,800円 | 15,000円 |
| 登記事項証明書 | 600円 | 600円 |
| 小計 | 20,400円 | 15,600円 |
| 合計 | 36,000円 | |
※上記参考事例は、新築建物課税価格1千万円、一般の住宅用家屋証明書利用の場合です。
※連件、管轄、登記内容等により登記費用は異なる場合があります。
※別途、交通費、送料等の実費が必要な場合があります。
住宅用家屋証明(新築・戸建の所有権保存登記の場合)の取得要件
所有権保存登記で登録免許税の税率軽減を受けるには、租税特別措置法第72条の2他の要件を満たさなければなりません。
対象となる建物には、新築と未使用建物がありますが、ここでは、よくある新築・戸建の場合の住宅用家屋証明についての要件をまとめておきます。
全体面
- 1.自己(個人)の居住用
- 2.新築後1年以内に所有権保存登記申請
物件面
- 1.床面積50㎡以上(上限なし)
- 2.登記記録種類が原則、「居宅」。
- 「居宅」以外の種類(「事務所」・「店舗」・「倉庫」など)を含む併用住宅の場合、
- それらが全体の床面積の10%以内であること。
- ※「物置」や「車庫」の場合、10%超でもOK。(住宅に付随するものとして)
- 3.特定認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合、認定申請書写しと認定通知書の写し
- が添付できること。
京都の所有権保存登記ご依頼者の声
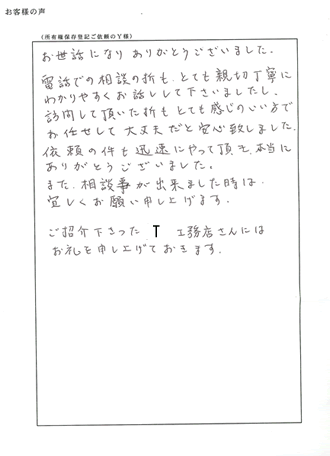
お世話になり、ありがとうございました。
電話での相談の折も、とても親切丁寧にわかりやすくお話しして下さいましたし、訪問して頂いた折もとても感じのいい方で、お任せして大丈夫だと安心致しました。
依頼の件も迅速にやって頂き、本当にありがとうございました。
また、相談事が出来ました時は、宜しくお願い申し上げます。
ご紹介下さったT工務店さんにはお礼を申し上げておきます。
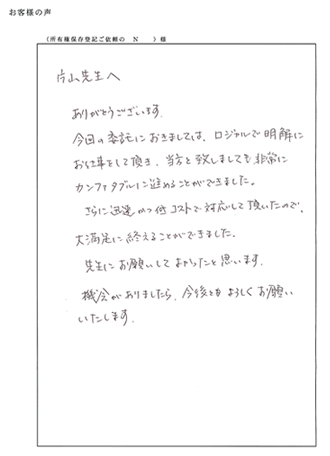
片山先生へ
ありがとうございます。
今回の委託におきましては、ロジカルで明解にお仕事をして頂き、当方と致しましても非常にカンファタブルに進めることができました。
さらに、迅速かつ低コストで対応して頂いたので、大満足に終えることができました。
先生にお願いして、よかったと思います。
機会がありましたら、今後とも、よろしくお願いいたします。