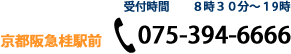- HOME
- >
- 業務案内
- >
- 会社設立変更・法人登記
- >
- 一般社団・財団法人設立
一般社団・財団法人設立
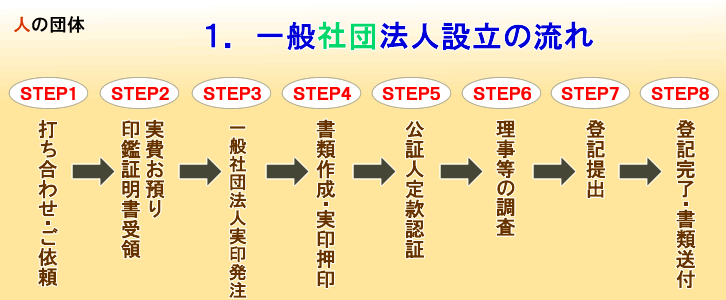
1.一般社団法人の設立
平成20年の法施行から、上記の流れに沿って、公証人の定款認証を経て、設立登記を申請するだけで、主務官庁の許可なく、簡易に、一般社団法人を成立できるようになりました。
5年間の移行期間も終わり、公益社団法人となるには、一般社団法人設立を経てから公益認定(公益認定等委員会の認定)を受けるしか道がなくなりました。
その公益認定等委員会の認定を受けるには、セミナー等による一般人への開放度合いや情報開示の強化等公益性維持のための負担が重く、また、理事会や監事の設置が必須となるなど そのハードルは高いと言えます。
ここでは、公益法人ではなく、比較的小規模で、簡易にできる、一般社団法人の設立に限定して、説明しています。
一般社団法人特有のものに、下記事項が挙げられます。
- 1.社員は2名以上必要。法人も可
- 2.理事は最低1名必要(その場合、兼代表理事)。法人で無い社員が兼ねることも可
- 3.監事、理事会等は任意。ただし、理事会設置は理事3名以上、監事1名以上必要
- 4.剰余金の分配はできない。(給与や役員報酬は当然、可)
- 5.出資は不要。基金は任意だが、定めれば返還義務生じる
- 6.目的は自由。収益事業も可
- 7.一定の要件満たせば、税法上の特典も
- 8.主務官庁の許可なく、設立登記だけで成立。
一般社団法人の設立時概要
一般社団法人の設立には、下記概要を決めていきます。
- 1.設立の趣旨・将来の展望(収益事業、将来の公益化、非営利型、事業規模の確認)
- 2.目的・事業
- 3.設立希望日
- 4.名称
- 5.主たる事務所
- 6.事業年度
- 7.社員(2名以上)
- 8.役員等の構成(理事1名以上・代表理事・監事・会計監査人)
- 9.役員の任期
- 10.社員の資格の得喪に関する規定
- 11.理事等の責任免除・外部理事等の責任制限の定め
- 12.基金について
よくある質問の答え
名称に使用できる文字
- 名称に使用できる文字は下記の通り決められています。
- 「一般社団法人」の文言は必ず入れなければならないので、前か後か、お決めください。
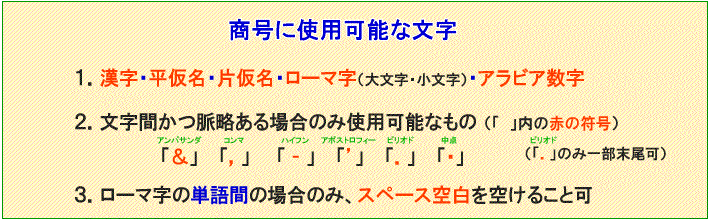
理事、監事の任期
一般社団法人において、理事、監事の任期は、定款の相対的記載事項となっています。
理事の任期は、原則、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」です。
ただし、上記理事の任期は、定款又は社員総会決議により、短縮することができます。
監事の任期は、原則、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」です。
ただし、上記監事の任期は、定款により、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで」とすることを限度として短縮することができます。また、任期満了退任する監事の補欠として選任された者の任期を、任期満了した者の任期の満了するまでとすることも可能です。
登記事項
主な登記事項は、次のとおりです。
- 1.名称
- 2.主たる事務所
- 3.目的等(目的・事業)
- 4.理事・監事・会計監査人の氏名、代表理事の住所・氏名、理事会・監事設置法人の旨等
- 5.理事等の責任免除、外部理事等の責任制限の定めあれば、その定め
- 6.公告の方法
非営利型一般社団法人
社団法人のうち、法人税の優遇度合いにより、公益社団法人、非営利型一般社団法人及び通常の一般社団法人の3つに分けることができます。
そのうち、公益社団法人以外でも、非営利型一般社団法人の要件を満たすと、34種の収益事業だけにしか課税されないので、税務上有利になるといえます。
非営利型一般社団法人には、「非営利性が徹底された一般社団法人」と「共益的活動を目的とした一般社団法人」、の2つに分類されます。それぞれ、下記要件を全て満たさなければなりません。実際の運営については、税務署、税理士にお尋ねください。
(詳しくは、財務省:非営利法人に対する課税の取扱い、国税庁:法人税通達)
「非営利型が徹底された社団法人」の要件
- 1.定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
- 2.定款に、解散時に残余財産が国や地方公共団体、公益法人等に帰属する旨の定めがある
- こと
- 3.前2項を行うことを決定したり、行ったことがないこと
- 4.各理事について、理事及びその理事の親族等特殊関係にある者である理事の合計数が、
- 理事総数の3分の1以下であること
「共益的活動を目的とした社団法人」の要件
- 1.主たる目的が、会員の相互支援、交流、連絡等、会員に共通する利益を図るものである
- こと
- 2.定款に会費の額の定めがあるか、社員総会等で定める旨の定めがあること
- 3.主たる事業として収益事業を行っていないこと
- 4.定款に、特定の個人又は団体に、剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこ
- と
- 5.定款に、解散時に残余財産が、特定の個人又は団体に帰属する旨の定めがないこと
- 6.1項から5項及び7項の全ての要件に該当した期間内に、特定の個人又は団体に、剰余
- 金の分配その他の方法により、特別の利益を与えることを、決定したり与えたことがな
- いこと
- 7.各理事について、理事及びその理事の親族等特殊関係にある者である理事の合計数が、
- 理事総数の3分の1以下であること
基金
一般社団法人設立時における基金とは、設立時社員により拠出された金銭その他の財産で、法人としては返還義務を負う借金のようなものです。その基金の返還に係る債権には、利息を付することができません。
なお、基金の規定を定款に規定するか否かは任意です。
調査
設立時理事及び監事は、選任後遅滞なく、一般社団法人の設立手続きが法令又は定款に違反していないことを調査しなければなりません。
ただし、これを証する調査報告書は登記の添付書類とはなっていませんが、違反があれば設立時社員に通知する義務があります。
一般社団法人設立登記に必要な書類等
一般社団法人設立登記に最低限必要な書類等は以下のとおりです。
- 1.定款
- 2.主たる事務所を決定したことを証する書面
- 3.就任承諾書
- 4.委任状
- 5.理事の印鑑証明書 各1通(代表社員は2通)
- 6.印鑑届出書
- 7.法人の実印とする印鑑
2.一般財団法人の設立
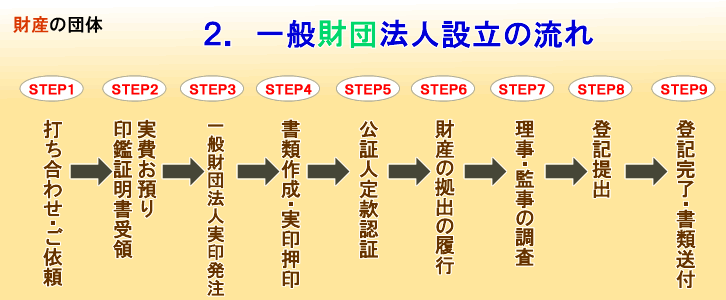
平成20年の法施行から、上記の流れに沿って、公証人の定款認証を経て、財産の拠出の履行、設立登記を申請するだけで、主務官庁の許可なく、簡易に、一般財団法人を成立できるようになりました。
ここでは、公益法人ではなく、比較的小規模で、簡易にできる、一般財団法人の設立に限定して、説明しています。
一般財団法人特有のものに、下記事項が挙げられます。
- 1.社員いないので設立者1名で設立可(遺言による場合、遺言執行者)
- 2.評議員3名以上、理事3名以上(内1名代表理事)、理事会、監事、評議員会は必須
- 3.評議員と理事・監事の兼任不可
- 4.評議員が理事・理事会を監督
よって、監督される理事・理事会が評議員を選任する旨の定款規定は無効 - 5.設立者に剰余金や残余財産の分配を与える旨の定款規定は無効
- 6.設立時、300万円以上の金銭等の財産拠出必要
- 7.基本財産の滅失や、純資産額が設立後2事業年度継続して6項の財産価額を下回れば
- 解散
- 8.一定の要件満たせば、税法上の特典も
- 9.遺言による一般財団法人の設立、可
- 10.主務官庁の許可なく、設立登記だけで成立
- 11.社団法人にある基金はないが、基本財産がある
一般財団法人の設立時概要
一般財団法人の設立には、下記概要を決めていきます。
- 1.設立の趣旨・将来の展望(収益事業、将来の公益化、非営利型、事業規模の確認)
- 2.目的・事業
- 3.設立希望日
- 4.名称
- 5.主たる事務所
- 6.事業年度
- 7.設立者(1名で可)の拠出する財産とその価額
- 8.役員・評議員の構成(理事3名以上・代表理事・監事1名以上・評議員3名以上)
- 9.役員・評議員の任期
- 10.基本財産について
- 11.責任免除・責任限定契約の定め
よくある質問の答え
名称に使用できる文字
- 名称に使用できる文字は下記の通り決められています。
- 「一般財団法人」の文言は必ず入れなければならないので、前か後か、お決めください。
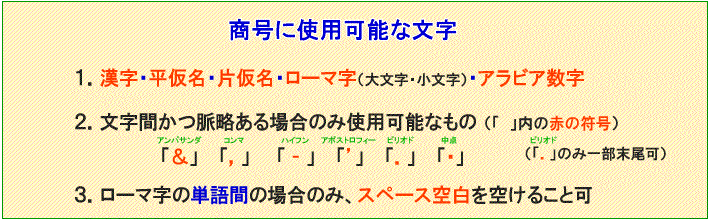
理事、監事、評議員の任期
一般財団法人において、理事、監事、評議員の任期は、定款の相対的記載事項となっています。
理事の任期は、原則、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」です。
ただし、上記理事の任期は、定款により、短縮することができます。
監事の任期は、原則、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」です。
ただし、上記監事の任期は、定款により、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」とすることを限度として短縮することができます。また、任期満了退任する監事の補欠として選任された者の任期を、任期満了した者の任期の満了するまでとすることも可能です。
評議員の任期は、原則、「選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」です。
ただし、上記監事の任期は、定款により、「選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで」、伸長することができます。また、任期満了退任する評議員の補欠として選任された者の任期を、任期満了した者の任期の満了するまでとすることも可能です。
登記事項
主な登記事項は、次のとおりです。
- 1.名称
- 2.主たる事務所
- 3.目的等(目的・事業)
- 4.評議員・理事・監事・会計監査人の氏名、代表理事の住所・氏名、会計監査人設置法人
- の旨等
- 5.理事等の責任免除、外部理事等の責任制限の定めあれば、その定め
- 6.公告の方法
非営利型一般財団法人
社団法人のうち、法人税の優遇度合いにより、公益財団法人、非営利型一般財団法人及び通常の一般財団法人の3つに分けることができます。
そのうち、公益財団法人以外でも、非営利型一般財団法人の要件を満たすと、34種の収益事業だけにしか課税されないので、税務上有利になるといえます。
非営利型一般財団法人には、「非営利性が徹底された一般財団法人」と「共益的活動を目的とした一般財団法人」、の2つに分類されます。それぞれ、下記要件を全て満たさなければなりません。実際の運営については、税務署、税理士にお尋ねください。
(詳しくは、財務省:非営利法人に対する課税の取扱い、国税庁:法人税通達)
「非営利型が徹底された財団法人」の要件
- 1.定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること
- 2.定款に、解散時に残余財産が国や地方公共団体、公益法人等に帰属する旨の定めがある
- こと
- 3.前2項を行うことを決定したり、行ったことがないこと
- 4.各理事について、理事及びその理事の親族等特殊関係にある者である理事の合計数が、
- 理事総数の3分の1以下であること
「共益的活動を目的とした財団法人」の要件
- 1.主たる目的が、会員の相互支援、交流、連絡等、会員に共通する利益を図るものである
- こと
- 2.定款に会費の額の定めがあるか、社員総会等で定める旨の定めがあること
- 3.主たる事業として収益事業を行っていないこと
- 4.定款に、特定の個人又は団体に、剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこ
- と
- 5.定款に、解散時に残余財産が、特定の個人又は団体に帰属する旨の定めがないこと
- 6.1項から5項及び7項の全ての要件に該当した期間内に、特定の個人又は団体に、剰余
- 金の分配その他の方法により、特別の利益を与えることを、決定したり与えたことがな
- いこと
- 7.各理事について、理事及びその理事の親族等特殊関係にある者である理事の合計数が、
- 理事総数の3分の1以下であること
基本財産
基本財産とは、一般社財団法人の財産のうち、その事業を行うのに不可欠な財産をいい、定款に定めます。
基本財産は、その一般財団法人において、最低限、維持されなければならない財産であり、それにつき目的である事業を行うことを妨げるような処分をしてはいけないことになっています。
また、基本財産の滅失による事業の成功の不能は、一般財団法人の解散事由にあたります。
なお、基本財産の規定を定款に規定するか否かは任意です。
調査
設立時理事及び監事は、選任後遅滞なく、財産の拠出の履行が完了していること及び一般財団法人の設立手続きが法令又は定款に違反していないことを調査しなければなりません。
ただし、これを証する調査報告書は登記の添付書類とはなっていませんが、違反があれば設立者に通知する義務があります。
一般財団法人設立登記に必要な書類等
一般財団法人設立登記に最低限必要な書類等は以下のとおりです。
- 1.定款
- 2.主たる事務所を決定したことを証する書面
- 3.就任承諾書
- 4.委任状
- 5.理事、監事、評議員、設立者の印鑑証明書 各1通(代表社員は2通)
- 6.財産の拠出の履行を証する書面(金銭以外なら調査報告書も)
- 7.印鑑届出書
- 8.法人の実印とする印鑑
3.一般社団法人・一般財団法人 設立時の比較
| 一般社団法人 | 一般財団法人 | |
| 最低設立者数 | 社員2名 | 設立者1名 |
| 最低役員数 | 理事兼代表理事1名 | 評議員3名 理事3名 監事1名 |
| 機関 | 社員総会 | 評議員会 理事会 |
| 設立時最低財産 | 0円 | 300万円 |