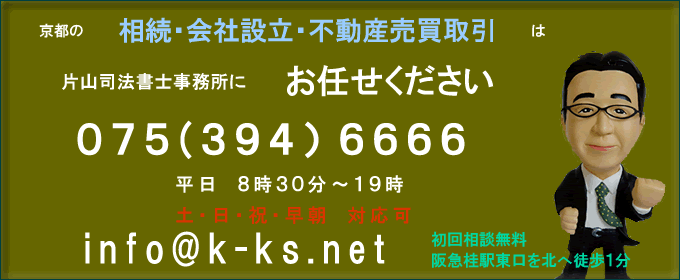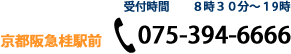共有物分割による持分移転
共有物分割による持分移転とは
不動産が共有持分関係にある場合、民法第256条1項により、いつでも共有物分割請求ができる(5年以内の不分割特約ある場合を除く)とされているとおり、共有物分割協議を経て不動産の所有権登記名義人を共有から単有にすることがあります。その場合にする登記申請が、持分を失う者を登記義務者、その持分を取得する者を権利者とする、持分全部移転登記となります。
なお、持分移転後、未だ単有とならず、共有関係が継続される場合であっても、単有に至る一過程として、共有物分割を登記原因とすることができるものとされています。また、登記の目的を所有権移転登記や所有権一部移転登記といった持分移転登記によらない登記はできないものとされています。(昭和36.1.17.民甲106)
共有物分割による持分移転登記に必要な書類
不動産の持分を失う(移転する)側
- 1.登記識別情報又は権利証
- 2.登記原因証明情報(※)
- 3.印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 4.固定資産税の評価証明書
- 5.委任状(※)
※ 当事務所にて作成致します。
不動産の持分を取得する側
- 1.住民票又は印鑑証明書
- 2.委任状(※)
※ 当事務所にて作成致します。
共有物分割を原因とする場合の登録免許税額の算出
共有物分割を原因とする持分移転登記の登録免許税の算出は適用される部分により税率が異なるなど複雑で、しかもたまにしかやらないため、忘れがちです。
要は、税率1000分の4となる税率が低くて済む部分は、「取得する土地の持分価額のうち、他の土地の持分移転で失う部分に対応する持分価額部分のみ」であり、それを超える部分についは税率1000分の20が適用されるということになります。
税率が1000分の4となるための要件は厳しく、以下の全てを満たさなければ1000分の4の税率は適用されません。
- 1.前提として分筆登記がなされていること
- 2.前項分筆後、初めての登記であること
- 3.持分を失う登記と、取得する登記は連件同時申請であること
- 4.各共有者が取得する持分は等価であること
共有物分割による持分移転登記に関する各種税金
1.所得税・贈与税
分割方法により、時価比率と持分比率から判断して持分に応じた分割であると認められない場合には、各税金の問題が発生する場合があるため、事前の十分な対応が必要となります。
2 .不動産取得税(共有持分を取得した方)
原則課税されませんが、分筆前の持分割合を超える部分については課税されるものとされています。(地法73の7二の三)
3.登録免許税(共有持分を取得した方)
不動産の名義変更(持分移転登記申請)の際、固定資産税評価額の持分相当部分につき1000分の4又1000分のは20の登録免許税がかかります。実際には、登記申請時に司法書士が代理で納めるため、登記申請時に報酬と共に司法書士に支払うことになります。