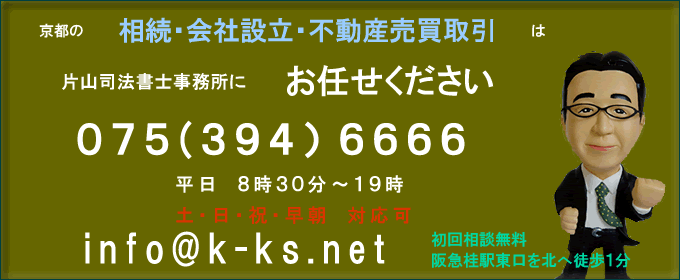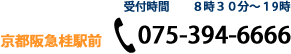贈与による所有権移転
贈与による所有権移転とは
贈与は、贈与する者(贈与者)と贈与される者(受贈者)との契約(贈与契約)により成立し、受贈者が受諾の意思表示をした日が登記原因日となります。
通常は無償贈与ですが、負担付贈与も認められており、その場合は負担特約を受諾した日が登記原因日付となります。
贈与による所有権移転に必要な書類
不動産を贈与する側(贈与者)
- 1.登記識別情報又は権利証
- 2.登記原因証明情報(贈与契約書等)(※)
- 3.印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 4.固定資産税の評価証明書
- 5.委任状(※)
※当事務所にて作成致します。
不動産を譲り受ける側(受贈者)
- 1.住民票又は印鑑証明書(※1)
- 2.委任状(※2)
※1 通常、贈与契約書に実印を押すため、両者に印鑑証明書を用意していただいています。
※2 当事務所にて作成致します。
未成年者の子に不動産を贈与する場合
未成年者が不動産の贈与を受ける契約を締結するには、未成年者の親が法定代理人(親権者)として同意又は代理をする必要があります。その際には、前述の添付書類の他、親子関係を証するため発行後3ヶ月以内の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要となります。
また、通常、親子間で利益相反となる場合には特別代理人を選任し、その者と贈与契約を締結する必要がありますが、親が贈与者となる場合でも、無償贈与の場合には利益相反とならないとされ、特別代理人の選任も必要ありません。
親が債務者となる住宅ローンが残っていて、抵当権が付いている不動産を贈与する場合でも、一般的には利益相反とはならない(債務者は親なので負担付とはならない)とされ、所有権移転登記はできますが、名義を変えるには事前に抵当権者である金融機関に承諾を得て行わないと最悪一括返済を迫られるため、事前に相談する必要があります。その場合、通常は担保提供、連帯保証等の書面に署名押印するため、未成年者では不可となり、また、これは利益相反となるため親も代理不可となり、結局、贈与による所有権移転登記以外のところで特別代理人の選任を要することになってしまうようで、中には贈与自体を断念される方もいらっしゃいます。
死因贈与契約とは
死因贈与契約とは、通常の贈与の効力を、贈与者の死亡によって生じさせる契約を言います。
贈与者の死亡によって効力が生じる点では遺贈と似ているため、民法554条により遺贈に関する規定を準用することも多いですが、単独行為と双方契約の違いから、判例では単独行為に基づく規定には準用しないものもあります。
登記手続き上の違いとしては、登記義務者が贈与者の相続人全員となる(執行者の指定が無い場合)ため、添付書類として相続人全員の印鑑証明書や戸籍等相続関係書一式が別途必要となります。
また、登記原因は、贈与者の死亡日の「贈与」とされ、「死因贈与」とは記載されません。
住宅取得等資金贈与の非課税特例とは
贈与による所有権移転の項目で挙げるには変ですが、注意していただきたいので一言載せておきます。
勘違いされる方が多いのですが、居住用として不動産そのものを贈与してもいいという規定ではありません。あくまでも、この特例は、「資金等」とあるように金銭そのものを贈与する際だけ適用されるものです。この点、居住用不動産の夫婦間贈与と違う点です。
平成31年6月30日までに、その年1月1日現在で20歳以上の者(受贈者。その年の合計所得金額二千万円以下要す)が、直系尊属である父母・祖父母等から、居住用家屋の取得に充てるための金銭贈与を受けるにあたり、一定の額までは贈与税が課されないと特例です。
適用には、原則、贈与の翌年3月15日までに入居し、本特例適用の贈与税の申告が必要となります。
また、取得する家屋については、床面積が50㎡以上240㎡以下でなければならず、耐震・省エネ要件によって、非課税限度額に違いがあるため、十分な注意が必要です。
贈与による所有権移転登記に関する各種税金
1.贈与税(譲り受けた方)
受贈者にかかります。暦年課税となり、その年、同じ者から受けた財産価格合計から基礎控除額110万円を控除した上で、該当する税率をかけたものが税額になります。
2 .不動産取得税(譲り受けた方)
通常かかります。
3.登録免許税(譲り受けた方)
不動産の名義変更(所有権移転登記申請)の際、固定資産税評価額の1000分の20の登録免許税がかかります。実際には、登記申請時に司法書士が代理で納めるため、登記申請時に報酬と共に司法書士に支払うことになります。
4.印紙税(書類作成者)
無償贈与の場合、各贈与契約書に200円の収入印紙を貼ることで納税します。