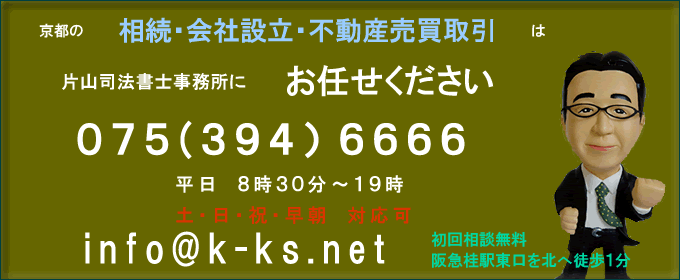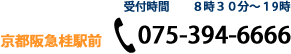- HOME
- >
- 業務案内
- >
- 相続・遺産整理業務・遺言
- >
- 相続放棄
相続放棄
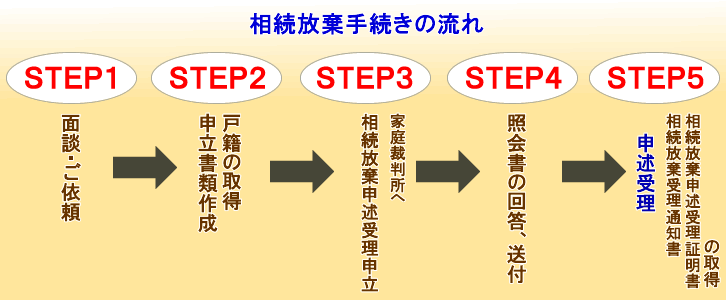
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が、自分のために開始した相続にかかる権利義務(プラス財産とマイナス財産)を確定的に消滅させる意思表示のことです。
その意思表示は、民法の規定により、自己に相続があったことを知ってから3ヶ月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所に申述(家庭裁判所に書類を提出)することが必要で、その申述受理の審判の成立によって、その効果が発生します。
なお、遺産分割協議で自分が何も相続しないことを、一般の方はよく、「相続を放棄した」と言われますが、これは相続人間だけで有効なもので、債務があるような場合には、相続人の一人として債権者に支払い請求をされてしまうので、注意してください。
相続放棄の効果
相続放棄の申述が受理された場合、その相続人であった者は、はじめから相続人でなかったことになります。
但し、この申述受理には既判力はないので、たとえ審判がなされても、債権者はその相続放棄の効力について争うことができます。
相続放棄を選択する理由としては、被相続人が第三者の連帯保証人になっていたり、借金が多い債務超過のような場合が一番多いようですが、遺産分割で他の相続人とかかわりたくない等他にもさまざまな理由があるため、相続放棄の理由はどのようなものでもよいとされています。
相続放棄が認められない場合とは
既に相続財産の一部を処分したり、相続財産を隠匿したり、処分により原形の価値を失うような行為をした(私に消費)ような場合には、単純承認とみなされ( 法定単純承認)、たとえ熟慮期間内に相続放棄受理の申し立をしても、不受理となり、放棄は認められません。
「処分」とは具体的にどのような行為か?
具体的には、預貯金の解約や保険金(死亡保険金除く)の請求受領、不動産の売却、賃貸(無償貸与除く)、債権取り立て、相続財産からの相続人固有の債務の弁済、相続財産に関する訴訟提起、遺産分割協議等がそれにあたります。
なお、保存行為や、葬式費用(高額で無い仏壇・墓石購入費の支払い含む)、後述の死亡保険金の請求受領、経済的価値の低い形見分け、無価値な物の廃棄処理のような行為は、「処分」にはあたらないとされています。但し、ケースバイケースで必ず認められるとは限らないので、相続放棄を考える場合には故人の財産には手をつけないのが原則です。
また、相続人の自己の財産から支出する相続債務の一部弁済は、相続財産の一部処分にあたらないとされた判例があります。相続債務の弁済や相続財産による相殺は保存行為と考えられるからでしょう。
死亡保険金は、相続放棄したらもらえない? 診断・入院・通院給付金は?
死亡保険金(相続人が受取人となっている)や退職手当金等は、民法上の相続財産ではなく、自己の固有の財産とみなされるため、放棄しても受け取れます。
但し、相続税法上はみなし相続財産として、課税の公平の見地から相続財産に組み入れて相続税額の算出を行います。
また、放棄した者は相続人ではないので各非課税控除もできません。
ただ、放棄した者も非課税限度額(500万円×法定相続人の数)計算の法定相続人の頭数には含まれるため、他の生命保険金等受取相続人の非課税控除には貢献することになります。
それに対し、がん保険等の診断給付金や、入院・通院給付金、自賠責保険金等のように、通常、受取人が被相続人となっているものは、前述の死亡保険金とは違い、相続人の固有の財産ではなく相続財産を形成するため、それらを請求・受領してしまうと、法定単純承認に当たり、相続放棄ができなくなるため、十分な注意が必要といえます。
借金が多くなるとわかっていて、放棄を考えているような場合には、くれぐれも、遺産分割協議や処分行為をしないよう、注意してください。
せっかく相続放棄受理申立てをしても、認められません。
相続放棄が認められる場合とは
前述の認められない場合とは逆に、下記要件を全て満たすような申立となれば、不受理になる可能性は低いと言えるでしょう。
ただ、処分にあたるか否かの判断は難しく、判例などに照らし、考えながら申立書類を作成しないと、つじつまがあわなくなるため、法律に詳しくないと難しい手続きかもしれません。
申述受理申立ては、一度きりしか認められず、やり直しがきかない一発勝負です。(但し、申述を却下する審判がなされた場合には、相続人は即時抗告ができます。)
その書類の可否で、数千万円の借金を負うか、免れるかが決まる場合もあるので、慎重な対応が望まれます。 但し、実際は財産を処分や隠匿したのに、していないと虚偽の申述をしたら、受理されないのは前述のとおりです。
- 1.意思能力・行為能力ある相続人自らが申述
- 2.相続人の真意による申述
- 3.熟慮期間内での申述
- 4.相続財産の処分をしていない
- 5.隠匿や私に消費といった行為をしていない
熟慮期間
熟慮期間の、「知ってから」の起算点は、いったい、いつでしょうか?
原則は、
相続開始の原因たる事実(死亡)と、自己が法律上の相続人となった事実を、併せて知ったとき
とされています。
例えば、親が死亡したような場合には、通常は、「死亡の日」から、と考えられます。
しかし、兄弟が1年前に死亡し、配偶者が相続人だったとした場合に、その配偶者が相続放棄をし、親も既に死亡しているため、兄弟である自分のところに債権者から借金を払えと通知してきたような場合は、死亡を知ったのは死亡当日ですが、自己が相続人となった事実を知った日は、配偶者が相続放棄をしたのを知った日となるので、債権者から通知を受けた日の翌日(初日不算入)から熟慮期間を計算することになります。
さらに、昭和59年に最高裁判決があり、
上記熟慮期間を過ぎていても、相続財産が全くないものと信じ、かつ被相続人の生活歴や疎遠状態等相続財産の有無を調査することが著しく困難な事情があって、相続人がそのように信じるのに相当な理由があると認められた事例では、熟慮期間は、「相続財産の全部若しくは一部を認識した時又は通常これを認識しうべき時から」起算すべきである
とされ、例外的に熟慮期間の起算点を繰り下げられた事例もあり、実務上は、処分と熟慮期間について、いろいろ考えながら対応しなければならないことがあります。
熟慮期間の伸長
熟慮期間の徒過によって、単純承認をしたとみなされてしまうため、財産がどれだけあるかすぐに調べられなかったり、債務の総額がわからないといったような場合には、熟慮期間を伸ばすことができます。
注意すべきは、この伸長申立も、家庭裁判所に申立てが必要で、必ず熟慮期間内にしなければなりません。
熟慮期間を過ぎてから伸ばしたいと言ってもダメですので、十分注意してください。
家庭裁判所への相続放棄申述受理申立て
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、申述のため、添付書類と共に申述書を提出しなければなりません。
長く音信不通で付き合いの無かった親族について、その債権者からの通知で初めてその親族が亡くなっていたこと、自分が相続人の一人であること、借金があったこと、を知った方からご依頼を頂きました。亡くなってから3ヶ月以上経ってはいましたが、問題はそこではなく、管轄の家庭裁判所がわからないことでした。除票や戸籍の附票は既に廃棄処分済で、全く付き合いが無かったので最後の住所地がわかりません。最後の手段として法務局に死亡届の記載事項証明書を請求するも、京都ではそのような事例では特段の理由があるとまでは言えず発行を拒否されました。ある程度確信が得られれば、廃棄済証明書と上申書で申述に至ることもあるのですが、この場合は結局、東京家庭裁判所 訟廷事件係に申述するしかなくなりました。
申述は郵送でも可能で、その場合には、日付は送付日を記載し、レターパックプラスや簡易書留で送ります。
また、限定承認と違い、相続人各自の判断で単独で行います。
放棄しようとする者が未成年者の場合には法定代理人となる親等が申立人となります。
ただし、相続人である未成年者とその親等が利害対立するような場合にはその親等は申述人となれず、家庭裁判所に別途特別代理人選任手続きが必要となります。
当事務所に相続放棄手続きをご依頼の場合、必要なもの
下記必要書類等は、よくある、親が死亡した場合の子が申述する場合のもので、最低限必要なものです。
内容により相違があり、また当事務所に手配できるものもございますので、最初のご相談時にご確認ください。
- 1.被相続人の死亡の記載のある戸籍全部事項証明書
- 2.被相続人の住民票除票(本籍地記載のあるもの)
- 3.申述人(放棄する人)の戸籍全部事項証明書
- 4.申述人の住民票抄本(本籍地記載のあるもの)
- 5.申述人の本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)
- 5.認印(朱肉で押すもの)
- 6.預り金1万円
家庭裁判所に提出する戸籍記載の死亡日から既に3ヶ月が経過している場合に、「知ってから」の起算日が問題になります。 いつ知ったかは本人にしかわからないため、家庭裁判所に申述の申立てをする際、「私が被相続人の死亡を知った日は死亡した日ではなく、債権者からこの通知があった日です」と立証するため、親と疎遠で死亡を知りえなかったことなどを疎明した上で、債権者からの通知書等を添付して、申請する必要がでてきます。
申立て後
約1~2週間で家庭裁判所から照会書類が届きますので、その書類に必要事項を記入し、署名・押印(申述書に押したものと同じ印鑑)のうえ返送します。 家裁で認められれば受理通知が郵送されてくるので、必要に応じ相続放棄申述受理証明書の交付申請をすれば完了となります。なお、家裁において特に問題無いと思われる事件については照会書なしでいきなり申述受理通知書が届くこともあります
当事務所にご依頼いただき、相続放棄手続きをされた方の声を掲載しています。
(詳しくはご依頼者様の声 相続放棄)
以前、書類を提出した放棄者が、裁判所から届いた封筒(照会書)を開けずに放置していたことがありました。
事前に照会書が着いたら返送する必要がある旨お伝えし、都度、着いたかどうか確認していたのですが、
差出人が家庭裁判所名でなく書記官個人名の茶封筒で届いたため、「知らない人からの封筒なので時間があれば見よう」と思い、放置していたそうです。
照会書等は放棄される方ご本人の住所地に送付されますので、ご注意ください。
相続放棄がある場合の相続登記手続き
相続人の中で、相続放棄を受理された方がいる場合の、相続登記申請には、相続申述受理通知書ではなく相続申述受理証明書が必要です。
法務局によっては通知書で通るところもあるようですが、原則、証明書が必要となりますので、放棄された方から受理証明書までお預かりください。
詳しくは、相続登記(不動産名義変更)
相続放棄(京都家裁) 費用
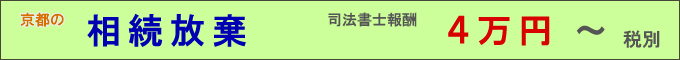
熟慮期間内の場合
| 内容 | 司法書士報酬 | 実費 | |
|---|---|---|---|
| 相続放棄相談 | 相続放棄についてのご相談から、申述書や照会書の記載方法などのサポートを含みます | ご依頼の場合、 無料 |
― |
| 戸籍取得 | 遠方などでご自身で取れない場合、当職が職権でとることができます | ご依頼の場合、 1,000円/通 |
ー |
| 書類作成 | 申述受理申立書面案などの作成 | 40,000円 | ― |
| 通信費等 | 家庭裁判所に提出する収入印紙代、切手、その他通信費を含みます | ― | 3,000円 |
※消費税は別途必要です。
※熟慮期間経過後の場合や熟慮期間の伸長申立をされる場合、別途必要となります。
※家庭裁判所に提出する収入印紙・切手
放棄する相続人ひとりにつき、1,270円
(内訳:収入印紙800円、84円切手5枚、10円切手5枚/令和2年京都)
相続放棄ご依頼者の声
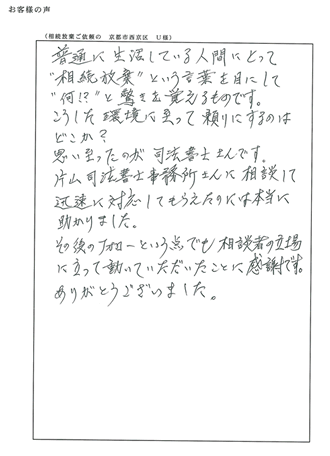
普通に生活している人間にとって、「相続放棄」という言葉を目にして、「何?」と驚きを覚えるものです。
こうした環境に至って頼りにするのはどこか?
思い至ったのが司法書士さんです。
片山司法書士事務所さんに相談して迅速に対応してもらえたのには本当に助かりました。
その後のフォローという点でも相談者の立場に立って動いていただいたことに感謝です。
ありがとうございました。
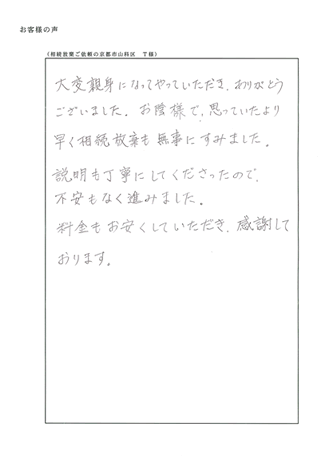
大変親身になってやっていただき、ありがとうございました。お陰様で、思ったより早く相続放棄も無事にすみました。
説明も丁寧にしてくださったので、不安もなく進みました。
料金もお安くしていただき、感謝しております。
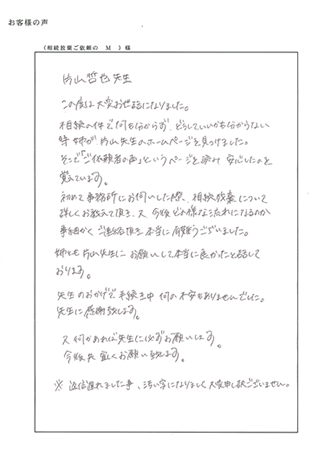
片山哲也先生
この度は大変お世話になりました。
相続の件で何も分からず、どうしていいかも分からない時、姉が片山先生のホームページを見つけました。
そこで、「ご依頼者の声」というページを読み、安心したのを覚えています。
初めて事務所にお伺いした際、相続放棄について詳しくお教え頂き、又、今後どの様な流れになるのか事細かくご連絡頂き本当に有難うございました。
姉とも片山先生にお願いして本当に良かったと話しております。
先生のおかげで手続き中、何の不安もありませんでした。先生に感謝致します。
又何かあれば先生に必ずお願いします。
今後共宜しくお願い致します。
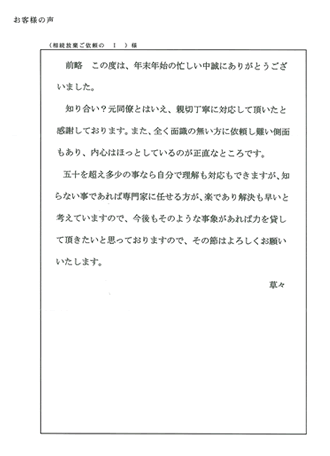
前略 この度は、年末年始の忙しい中、誠にありがとうございました。
知り合い?元同僚とはいえ、親切丁寧に対応していただいたと感謝しております。また、全く面識の無い方に依頼し難い側面もあり、内心はほっとしているのが正直なところです。
五十を超え、多少の事なら自分で理解も対応もできますが、知らない事であれば専門家に任せる方が、楽であり解決も早いと考えていますので、今後もそのような事象があれば力を貸して頂きたいと思っておりますので、その節はよろしくお願いいたします。
早々
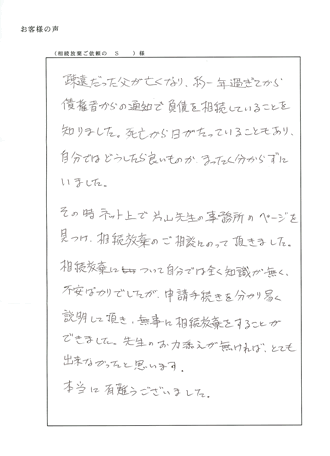
疎遠だった父が亡くなり、約1年過ぎてから、債権者からの通知で負債を相続していることを知りました。死亡から日がたっていることもあり、自分ではどうしたら良いものか、まったくわからずにいました。その時、ネット上で片山先生の事務所のページを見つけ、相続放棄のご相談にのって頂きました。相続放棄について自分では全く知識が無く、不安ばかりでしたが、申請手続きを分かり易く説明して頂き、無事に相続放棄をすることができました。先生のお力添えが無ければ、とても出来なかったと思います。本当に有難うございました。
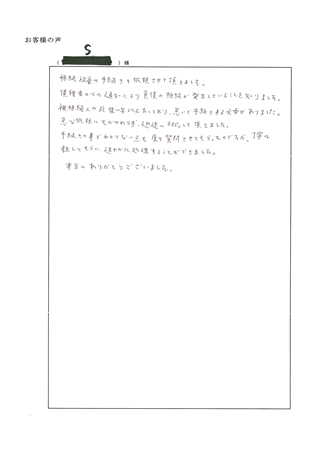
相続放棄の手続きを依頼させて頂きました。債権者からの通知により負債の相続が発生していることを知りました。被相続人の死後一年以上たっており、急いで手続きをする必要がありました。急な依頼にもかかわらず、迅速に対応していただきました。手続きの事でわからない点も度々質問させてもらったのですが、丁寧に教えてもらい、速やかに処理することができました。本当にありがとうございました。
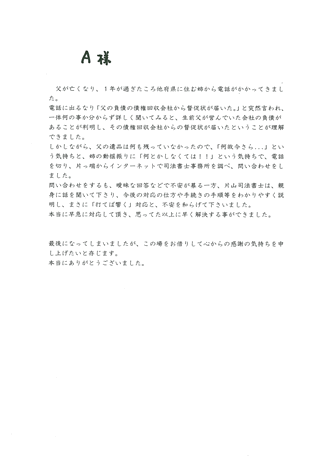
父が亡くなり、1年が過ぎたころ他府県に住む姉から電話がかかってきました。電話に出るなり、「父の負債の債権回収会社から督促状が届いた。」と突然言われ、一体何の事か分からず詳しく聞いてみると、生前父が営んでいた会社の負債があることが判明し、その債権回収会社からの督促状が届いたということが理解できました。しかしながら、父の遺品は何も残っていなかったので、「何故今さら・・・」という気持ちと、姉の動揺振りに、「何とかしなくては!!」という気持ちで、電話を切り、片っ端からインターネットで司法書士事務所を調べ、問い合わせをしました。問い合わせをするも、曖昧な回答などで不安が募る一方、片山司法書士は、親切に聞いて下さり、今後の対応の仕方や手続きの手順をわかりやすく説明し、まさに「打てば響く」対応と、不安を和らげて下さいました。本当に早急に対応して頂き、思っていた以上に早く解決する事ができました。最後になってしまいましたが、この場をお借りして心からの感謝の気持ちを申し上げたいと存じます。本当にありがとうございました。