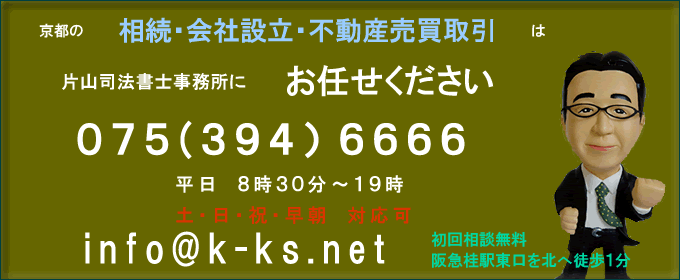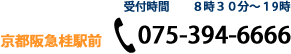- HOME
- >
- 業務案内
- >
- 相続・遺産整理業務・遺言
- >
- 遺産整理業務
遺産整理業務
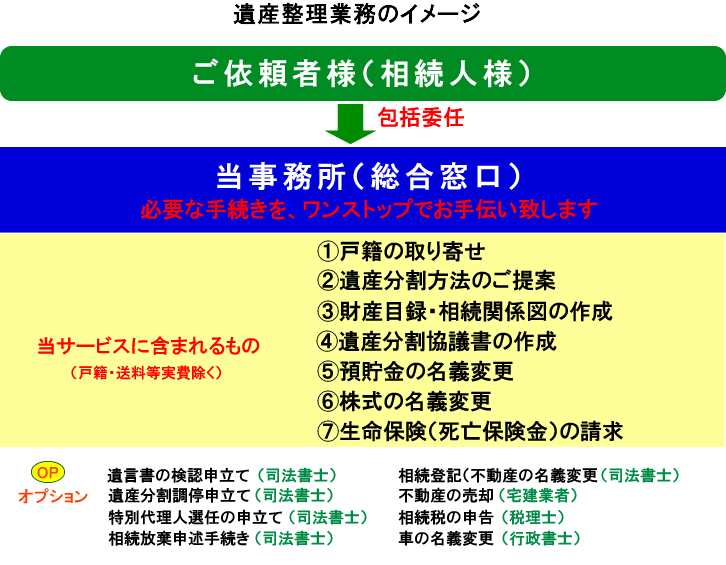
遺産整理業務について
ここでいう遺産整理業務とは、法律上、弁護士、司法書士、信託銀行(信託銀行では法律相談ができません)だけが、業としてすることが認められている包括的な遺産手続き業務のことです。
つまり、相続登記や、相続税の申告、車や預貯金の名義変更だけ、という個別事務処理ではなく、相続財産の全てについて相続人全員から依頼を受けて、遺産管理人(相続手続きに関する相続人全員の代理人)となって行う遺産承継全般に関する業務のことを指します。
特定の相続人が主導して事務処理を行うことは、ともすれば他の相続人の利益を害したり、必要な情報を皆に伝えずに処理してしまうといった可能性も秘めているため、相続人全員に対し、公正な立場で分配を行う法律専門職が求められていました。
イメージとしては、信託銀行が行っている業務と同様と考えていただいて結構ですが、信託銀行の業務につき、手数料が最低でも100万円以上することや、専門分野の手続きについては、司法書士(相続登記)や税理士(税務申告)、弁護士(紛争・裁判)等に別途費用が必要となってしまうことは、あまり知られていません。
信託会社への依頼を考えられる方のほとんどが、不動産を相続されると考えられますので、それでしたら始めから司法書士に依頼する方が、コスト面・スピード面で有利かと思われます。
当事務所では、信託銀行が対応できない、土・日・祝・早朝・夜間にも対応してます。
司法書士法第29条及び司法書士法規則第31条において、司法書士は高い倫理観のもと、財産管理業務や成年後見業務を、附帯業務(業)として、反復継続して行うことができる旨、規定されています。
士業としてこの法律事務が認められているのは、弁護士と司法書士のみで、税理士や行政書士はすることができません。
なお、遺産整理業務の一部として、相続税の申告等他士専業業務が必要となった場合には、税理士等担当する者をご紹介させていただきますので、その方と個別契約をしていただくことになります。
このような方に遺産整理業務をおすすめ致します
- 1.多忙で、時間的な余裕がない場合
- 2.相続人が多く、遠方におられる場合
- 3.遺言書があるがどのように手続きすればいいかわからない場合
- 4.遺産分割協議のやり方がわからない場合
- 5.相続財産の種類が多い場合
- 6.不動産の処分(売却)を伴うような場合
- 7.専門家に入ってもらって、他の相続人ともめずに分配したいような場合
具体的な遺産整理業務の流れ
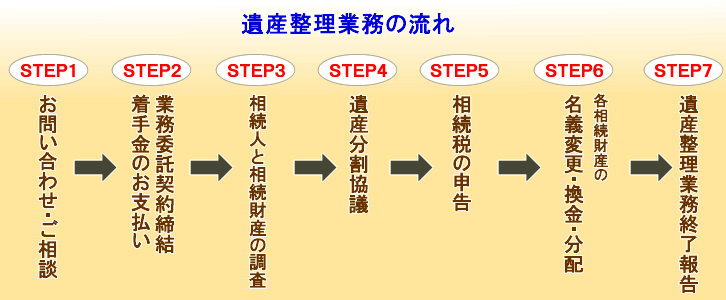
1.ご相談
まずはじっくりお話をお聞きしますので、リラックスしてお越しください。
当事務所のネットワークには、京都で活躍する弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー、不動産業者など多くの専門家がいますので、多方面に渡る業務をワンストップで行うことができます。
2.契約
ご相談でご案内した手続きプランに納得いただけましたら、相続人代表の方と当事務所司法書士の間で業務委託契約を交わし、着手金をお預かりすることで、遺産整理業務がスタート致します。
3.相続人と相続財産の調査
相続手続きで真っ先に取り組むことが、人(相続人)ともの(相続財産)の確定です。
相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を調査します。
並行して、相続財産につき、聞き取り等により確認し、登記事項証明書、名寄帳、固定資産税評価証明書、路線価図、金融機関の残高証明書等を手配し、財産目録を作成していきます。
相続人の数と財産の概要がわかると、相続税の申告が必要か否かが判明します。
相続税の申告が必要な場合、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければならず、その際、遺産分割協議が成立していない(未分割)場合には、不利益(配偶者の相続税額軽減や小規模宅地等の減額を受けられなくなります)を被るので、その後のスケジュールをしっかりと組んで調整していくことになります。
なお、遺言の有無、相続放棄・限定承認の選択についても、手続きを急ぐ必要があるため、この手続きの中で確認し、対応していくことになります。
生命保険金(死亡保険金)は受取人固有の財産(被相続人が保険料の一部でも支払っていた場合、相続税の課税対象にはなります)となりますので、請求手続きを急ぐ場合には、この時点で手続きをする場合もあります。
4.遺産分割協議
遺言がある場合は、遺産分割協議でなく遺言が優先(遺言書に記載無きもの、遺言執行の対象とならないものは除く)されますので、内容を確認します。
但し、それが自筆証遺言の場合には、勝手に開封することはできず、家庭裁判所に遺言書検認手続きを申し立てる必要があり、その際、後の手続きのため遺言済証明書を取得しておきます。
遺言によらない場合には、遺産分割協議を行い、当事務所にて作成する遺産分割協議書に署名、押印することになります。
相続人中、未成年者がいる場合、家庭裁判所にて特別代理人選任手続きが必要となる場合がありますので、必要であれば、この時点で申し立てることになります。
なお、残念ながら遺産分割協議において合意できないような場合には、家庭裁判所の遺産分割調停、裁判、一時保留などから選択していただくことになります。
5.相続税の申告
相続税の申告が必要となった場合、相続税の申告に慣れた税理士に依頼されることをお勧めしています。今までは申告する人も限られていたため(総相続件数の約4%)、一度もやったことがない税理士も多数おられます。
当事務所にてご紹介することもできますし、ご本人が直接依頼されても結構です。
なお、平成27年1月1日以後に発生する相続についての基礎控除額が、「3千万円+(6百万円×法定相続人の数)」に縮小されることが決まっており、相続税を申告すべき人が増えることが予想されています。
(平成27年からの相続新税制について詳しくは、別サイト:京都相続登記サポート|気になる税制改正)
6.各相続財産の名義変更、換金、分配
預貯金・株式等名義変更・換金・分配、車、ゴルフ・リゾート会員権等の名義書き換えを行います。
不動産ついては、法務局に相続登記(不動産名義変更)を申請し、その後、売却が必要でしたら、そのまま売却手続きに移行します。
7.遺産整理業務終了報告
業務のご報告を行い、かかった費用と当事務所報酬の精算を行い、手続き終了となります。
遺産整理業務(京都) 受託費用
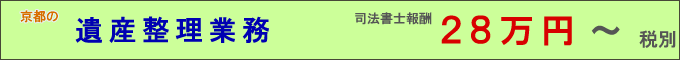
※申立用印紙代・切手、戸籍取得費用、通信費等は別途必要です。