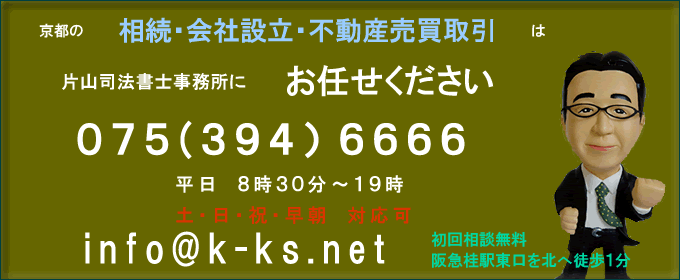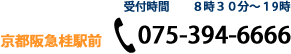居住用不動産の夫婦間贈与
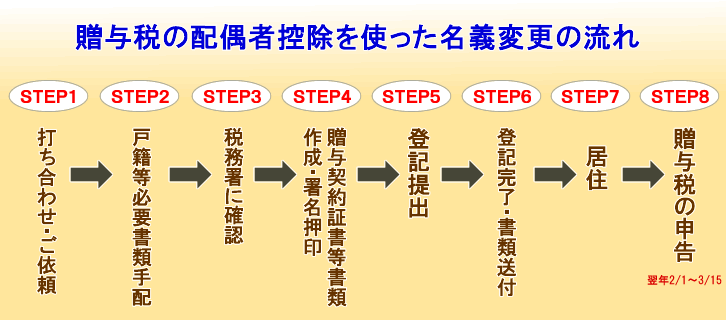
居住用不動産の夫婦間贈与とは
ここで取りあげる居住用不動産の夫婦間贈与とは、、婚姻期間20年超の夫婦間で、居住用不動産かそれを取得するための金銭(翌年3月15日までに実際に取得必要)を贈与した場合に受けられる贈与税の配偶者控除という特例のことをいいます。
贈与税の申告は必須で、該当すれば、基礎控除110万円と併せて、最高2,110万円の控除が受けられます。
相続税の基礎控除の引き下げなどにより、将来、相続税が課せられる人が増えるといわれていますので、今後さらに生前にこの特例を利用する人が増えると思われます。
また、生前贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものは相続財産に加算して相続税を計算する必要がありますが、この特例により贈与された財産は、相続開始前3年以内であっても相続税を計算する際の相続財産に加算されない、というメリットもあるため、相続税対策としても使えます。
控除の範囲内でより多く贈与したい場合、税金上、取得資金を贈与するより居住用不動産の現物を贈与する方が有利といわれています。
それは、評価する際の金額に差ができるためです。
金銭の場合、評価はそのままですが、不動産の場合には、路線価(土地)や固定資産税評価額(建物)で評価されます。
通常、路線価は公示価格の8割、建物の固定資産税評価額は建築費の5~7割程度(新築の場合)で評価されているといわれていますので、金銭が10割と考えると、その分、評価が下がることになります。
具体的な評価計算は、税務署や税理士にお尋ねください。
居住用不動産の贈与税の配偶者控除を使った名義変更
居住用不動産の贈与税の配偶者控除の特例を使うには、前述のとおり贈与税の申告が必須であり、その際、実際に名義変更されたかどうかの確認として、不動産の登記事項証明書を添付しなければなりません。
そのため、名義変更が必要であり、それが、贈与を原因とした所有権移転登記になります。
その際、贈与する人を登記義務者、贈与を受ける人を登記権利者といいます。
居住用不動産の贈与税の配偶者控除を使った名義変更に必要な書類
不動産を贈与する側(登記義務者)
- 1.登記識別情報(又は権利証)
- 2.登記原因証明情報(贈与契約証書)
- 3.印鑑証明書(3ヶ月以内)
- 4.固定資産税の評価証明書
- 5.戸籍謄本
- 6.委任状
※贈与は契約ですので、契約書が必要です。当事務所にて作成します。
※委任状は、当事務所にて作成致します。
不動産の贈与を受ける側(登記権利者)
- 1.住民票
- 2.委任状
※委任状は、当事務所にて作成致します。
居住用不動産の贈与税の配偶者控除を使った名義変更の登記費用の目安
居住用不動産の贈与税の配偶者控除を使った名義変更(所有権移転登記)には、贈与する側、贈与を受ける側それぞれに、登録免許税や登記事項証明書等の実費と、司法書士報酬(消費税別途)がかかります。
登録免許税額は、「固定資産税評価額×2%」(下記事例の場合、1千万×2%=20万円)の要領で計算します。
不動産を贈与を受ける側(登記権利者)の登記費用
| 参考事例:内訳 | 司法書士報酬 | 登録免許税等実費 |
| 所有権移転登記 | 38,600円 | 200,000円 |
| 登記事項証明書 | 1,200円 | 1,200円 |
| 小計 | 39,800円 | 201,200円 |
| 合計 | 241,000円 | |
※上記参考事例は、土地1筆で、固定資産税評価額が1千万円の場合です。
※贈与契約証書を作成する場合、別途費用がかかります。
※連件、管轄、登記内容等により登記費用は異なる場合があります。
※別途、交通費、送料等の実費が必要な場合があります。
不動産を贈与する側(登記義務者)の登記費用
| 参考事例:内訳 | 司法書士報酬 | 登録免許税等実費 |
| 登記原因証明情報等書類作成費用 | 10,000円 | ― |
| 登記事項証明書 | 600円 | 600円 |
| 小計 | 10,600円 | 600円 |
| 合計 | 11,200円 | |
※上記参考事例は、土地1筆で、固定資産税評価額が1千万円の場合です。
※登記識別情報をお持ちで、有効証明等を請求する場合には、別途費用が必要となります。
※贈与契約証書を作成する場合、別途費用がかかります。
※連件、管轄、登記内容等により登記費用は異なる場合があります。
※別途、交通費、送料等の実費が必要な場合があります。
※前提登記として、所有権登記名義人住所氏名変更更正登記が必要になる場合があります。
詳しくは、住所・氏名変更登記
居住用不動産の贈与税の配偶者控除を使う場合の注意点
せっかく、配偶者のことを思ってやったのに、後で贈与税がかかったとなっては、大変です。
以下、ポイントを挙げておきまが、実際に行われる際は、事前に税務署や税理士にご相談されることをお勧めします。
- 1.贈与税の申告が必要。
- 2.名義変更(所有権移転登記)が必要。
- 3.婚姻期間満20年超の計算は、戸籍で確認。
- 4.金銭贈与の場合、要件あり。
- 5.同一配偶者に、一生に1回しか使えない。
- 6.2,110万円を超える分には、通常の贈与税がかかる。
- 7.土地の贈与額は、路線価での評価。補正計算が面倒。持分移転の場合、問題に。
- 8.贈与の年の翌年3月15日までに実際に居住し、引き続き居住する見込みまで必要。
- 9.贈与する不動産が建物の場合、築年数や床面積などの制限なし。
居住用不動産の贈与税の配偶者控除を使った名義変更に関する各種税金
2,110万円まで非課税。超える分には課税。
かかります。
不動産の名義変更(所有権移転登記申請)の際、かかります。
将来、居住用不動産を売却する可能性があり、その際、譲渡所得税がかなりかかる可能性があると考えられる場合、税金上、全て贈与せず、共有にしておく方が有利といわれています。
それは、居住用財産の3千万円特別控除を夫婦2人で使えることになるためで、その結果、合計6千万円までの売却益まで譲渡所得税がかからなくなります。
この場合注意すべき点は、建物がある場合には、建物も含めて贈与して、名義変更登記をしておくことです。
具体的な対策や税金計算は、税務署や税理士にお尋ねください。
居住用不動産の贈与税の配偶者控除による所有権移転登記ご依頼者の声
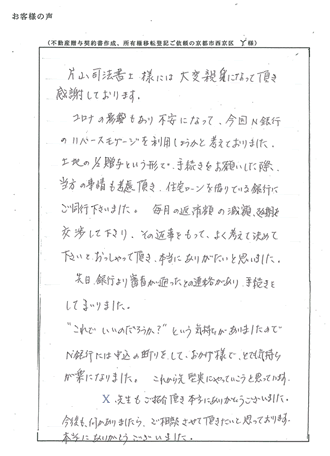
片山司法書士様には、大変親身になって頂き感謝しております。
コロナの影響もあり不安になって、今回、N銀行のリバースモゲージを利用しようかと考えておりました。土地の2分の1贈与という形で、手続きをお願いした際、当方の事情も考慮頂き、住宅ローンを借りている銀行にご同行下さいました。毎月の返済額の減額、延期を交渉して下さり、その返事をもって、よく考えて決めて下さいとおっしゃって頂き、本当にありがたいと思いました。先日、銀行より審査が通ったとの連絡があり、手続きをしてまいりました。
「これでいいのだろうか?」という気持ちがありましたので、N銀行には申込の断りをして、おかげ様で、とても気持ちが楽になりました。これから先、堅実にやっていこうと思っています。X先生もご紹介頂き、本当にありがとうございました。
今後も、何かありましたら、ご相談させて頂きたいと思っております。
本当にありがとうございました。
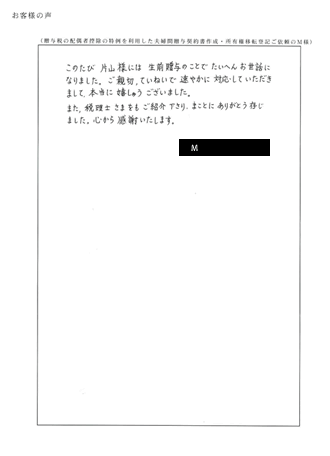
このたび、片山様には、生前贈与のことでたいへんお世話になりました。ご親切、ていねいで速やかに対応していただきまして、本当に嬉しゅうございました。
また、税理士さまをもご紹介下さり、まことにありがとう存じました。心から感謝いたします。
M夫婦